どうしてかな、と俺は放課後の誰もいない教室で自問自答する。 とは言え、答えなんて求めていないし、まあ現に納得する答えなんて出ていないし、かといって誰かに答えを求めた所で、全ての人間から、「そんなの当たり前だ」と言われるに違いない。 ああ、俺はもしかしたら「そんな事ないよ」とか言ってもらいたいのだろう。質問してるくせに、自分の言ってもらいたい事以外は受け付けない。自己中心的思考。勝手だ。きっと、そんなの誰一人たりとも言わないだろうけれど。 もしかしたら、もしかしたら、「励まして欲しいんだ。似てるって言ってくれ」とか素直に言っちゃえば、言われた人は変な顔しながらきっと、「似てる」って思っていなくても言ってくれるだろう。でもそんな事したくない。思ってなくたって言ってもらいたいけれど、言ってもらいたくない。 自分の本音を言うのはすごく恥ずかしい事なんだ。 似てる、似てない、似てる、いや、似てない、かな。 俺からすれば似てる気がするのに、周りから見れば、全ッ然似てないと言われる。(つっても実際に言われた事はないし、どちらかと言えばいつも比較ばっかされていた)アイツと似てて嫌だと思った時もあった。だけど、今は凄く、すっげー「似てるね」って言ってもらいたい。そうすれば俺は救われる。 代わりでもいいから、なりたいのだ。 かけられた声が耳を駆け抜け、ようやく俺は一人考え込んでいた事に気付いた。 「っああ、ごめん、姉崎、さん……えーと、何?」 「忙しいなら大丈夫だけど……」 「いや、ちょーっと考えてただけ。……委員会の話?」 握っていたシャープペンを置いて、俺はクラスメートである姉崎まもりの方へ向く。アメリカ人のクォーターである彼女の紅髪がゆれ、碧眼が俺を見る。俺の腕の下には明日までの数学の課題ノートが敷かれていた。 数学はあまり得意じゃなくて、どちらかと言うまでもなく文系人間なのだが、出されたからにはやらなきゃいけないだろう。生点で満点は難しいけれど、授業態度で何とかなる平常点で満点くらい取っとかなきゃいけない。面倒な話だ。 「えっとね、ほら、君が委員長になったから、コレ書かなきゃいけないみたい」 姉崎が俺に話しかける時は大抵委員会の話。と言っても、俺がクラスで嫌な意味で浮いてるだとか、姉崎は別に俺の事が嫌いな訳でもきっとなく(と信じたいと言うのが俺の妄想)、特別仲がいいという訳じゃないからだ。 差し出されたのは原稿用紙と、説明の書いてあるプリント。ザッと読んだ説明からするに、生徒会で月に一度発行されているプリントに、『風紀委員長としての意気込み』を書けというものだろう。 俺はため息をこっそりつきながらそれを受け取った。 「……やっぱり、こーゆうのあるんだ」 「そうみたいだね」 「こんなの誰も読みやしないってーの」 「まあまあ。……まあでも、委員会でまともに活動してるのって言えば風紀委員会くらいだしね」と、姉崎は憂うように言う。彼女は真面目なのだ。 「そんな委員会の委員長になったからにはしなきゃいけないですねえ」 わざとらしく俺は敬語を使うと、姉崎は笑った。 「でもごめんなさいね。元々は私が委員長になるはずだったのに……」 「いーよいーよ、つーか、姉崎さんは忙しいっしょ?俺は部活動してねえし、バイトくらいしか予定入ってないし、こんなの余裕!」 正式には、姉崎はもう部活を引退していた。泥門高校アメフト部マネージャー。それが彼女の先月までの肩書きだった。だけど、先月にはもう大きな大会も終わり、2年生は引退。あまり部活動が盛んではない泥門高は3年生ではなく、2年の秋になったら引退なのだ。だけど、いきなり残された1年だけで練習という訳にも行かず、毎日変わらずマネージャー業をしているようだった。 だから、今年の秋、つっても半月くらい前、前期分の委員会が終わるという時の3年生で引退式(と言ってもパーティなんてもんじゃなくて、ただ放課後集まっただけだけど)で、当時風紀副委員長だった姉崎が前委員長に推薦される前に、俺はまるでしゃしゃるように、「俺が委員長します」と立候補したわけだ。正直、こういうのは頼まれたりする側だったから、立候補は初めて…という訳ではなかったが、自分らしくなくあまりしない行動に少しドキドキした。 先ほど渡されたプリントと原稿用紙を眺め、何書こうか悩んでいると、姉崎は俺の隣の席(と言っても元々姉崎の席なのだが)に腰を下ろした。座ろうとした瞬間、紅髪が揺れ、ふんわりと香りがする。どうやら帰る支度をしているらしい。 「……ねえ、君、数学の宿題何ページまでだっけ?」 「んー……、23ページ、の上の問題まで」俺はすっかり鍋敷き状態だった課題ノートを捲った。「でも姉崎さんなら、終わってるんじゃないの?」 「ううんそんな! 今日帰ったらやるつもりなの」 「そっか。あのセンセー怖いから、ちゃんとやんなきゃね」 「……う、うん! そうだね」 姉崎は俺をまじまじと見た。 「………俺、何か変な事言った?」 「ち、違うの。なんだか当たり前の事なんだけど……、ほら、先生が怒る、とか、そういう事……」姉崎は説明しにくいのか、無意味にも身振り手振りを加える。 「……ああ、アメフト部にはヒル魔がいるからね」 「そう!何だかね、彼といると感覚が麻痺してくるみたいね」 という姉崎だが、顔は楽しそうだった。 真面目で優等生な姉崎まもりと正反対な蛭魔妖一。 蛭魔妖一は人を脅し奴隷にする当たり前な男子高校生、俺と同じ高校二年生。そんなのが本当に存在するのかと、他高の生徒は言うかもしれないけれどそうなのだ。脅す相手は同学年に留まらず、下級生そして上級生、挙句の果てに先生や校長まで。 「……何だか懐かしいな」 「ん?」 「こうして君と残ってる喋っているの、一年生の時ぶりじゃない?」 「ああ、そうだったね。……懐かしい」 一年生の頃も姉崎と同じクラスで、そして姉崎と同じ風紀委員に入っていた。その時はまだ姉崎はアメフト部には入っていなくて、泥門高校の悪の根源とされる蛭魔妖一をどうにか出来ないか二人で(というか色々案を出していたのは専ら姉崎一人だったんだけど)話し合ったりしていたのだ。 「まあ、あの時の俺らの話し合いは結局何も意味も成さなかったんだけどね」 「ふふ、そうね。でも、今は結構落ち着いてると思うの」 「そうだな。つーかヒル魔が落ち着いたのは、アメフトのおかげだよね」 「今年は……色々あったもんね」 「それに姉崎さんのおかげでもあるんじゃない?」 「えっ?私は何もしてないと思うけど……」 とは言っているけれど、無鉄砲なヒル魔を止める役に充分なったと思う。今まではずっと誰も彼も、「脅されたら怖い」と、ヒル魔に話しかけたり、止めたりしていなかったのに、姉崎はそんな事を顧みなかった。俺はというと、アイツにあまり関わりたくなかった。正直昔からアイツの姿を見るのも嫌で、一年姉崎があまりにも張り切っているから話し合いには付き合ったけれど、面と向かったことはそうなかった。 「――姉崎さん、って」 「うん?」 「ヒル魔の事、好きなの?」 姉崎は大げさに教科書やノートを落とした。 「え……な、なんでそうなるの……?」 「いや、噂になってたから、気になって」 「そ、そんな訳ないじゃない」 「でもさヒル魔の事、嫌いじゃないでしょ?」 「……去年まで、ううん、今年の4月までは嫌いだったけど、」姉崎は落ちたものを拾い集めた。「でも、真面目にアメフトをする人だって分かったの。もちろん、人を脅したり賭け事したりするのは絶っ対!認めないけどね」 「そっか」俺は今も嫌いだよ、と心の中で言う。 「君がそんな噂信じる人だなんて思ってなかった」 「アハハ、ごめんごめん、冗談だったのに」 「……分かってるよ。だって、去年もそんな事あったもんね」 去年まで『と姉崎まもりが付き合ってる』っていう噂が流れていた。別に俺が流した訳じゃない、し、まして姉崎の訳もない。 ただ一緒にいただけなのに噂は流れた。学生らしいお話だ。きっと今年の『蛭魔妖一と姉崎まもりが付き合っている』という噂もそういうものだろう。 「俺と姉崎さんがいると、よく『真面目コンビだ!』とか言われたしね」 「そうそう。褒め言葉何だか貶しているんだか分からなかったよね?」 「懐かしい」と、俺は先ほど言った言葉をもう一回言った。 「つーか、そう考えちゃ、姉崎さんも大変だよね。去年は俺で今年はヒル魔と」 「もう、ただの噂なのに」 「噂話は皆好きだしね」 真面目な姉崎と、真面目な俺。真面目な姉崎は風紀の乱れが気になり風紀委員会に入り、真面目な俺は、いや、『も』、流れで風紀委員会に入った。(まあ、真面目度で言えば同じ学年の雪光学の方がやばいと思うけれど) 俺は勉強は出来てる方だと思う。泥門は頭のいい学校じゃないから全国的にどうなのか知らないけれど。学年一位はどっかの悪魔が不動だから絶対どう頑張っても取れないが、俺はずっと二位。もちろん実力だろう。ヒル魔は普通に頭が良い。俺は幾ら頑張っても追いつかないくらいに。 「……今年なって思ったんだけどね、君とヒル魔君ってどこか似てるよね」 「………え?俺と、ヒル魔が?」 「あっ!その、悪い意味とかじゃなくて……う、うーん……でもどんな意味でもヒル魔君と似てるとか言われたくないよね……」 「いや、いいよ。どの辺りが?」俺は身を乗り出したい気持ちだった。 「どこ、って言うと上げにくいんだけど、その、雰囲気とかかなあ……でもヒル魔君の、あの邪悪な感じじゃなくて……」 「雰囲気」 「そう。二人とも、頭がいいし……ううーん……どう言ったらいいんだろう……」 姉崎は思い浮かんだ言葉をポンポンという。あまり考えがまとまっていないようだった。「でもね、」 「やっぱり君は君なんだよね」 「……ヒル魔と似てるって言われたの、中学入学してから初めてだ」 「えっ?同じ中学だったの?」 「そ、麻黄十三中。んーと、あと栗田とか武蔵とかとも同じだったっけな」 中学の時からアイツは相も変わらず俺とは真逆の問題児だった事をよく覚えている。 俺はそんな蛭魔妖一に負けたくなかった。問題児だけど頭が良いヒル魔は中学でもずっと学年一位。俺は万年二位。親は「がんばれば次きっと一位が取れる」と言ってくれたけれど、実際にヒル魔を見ればそんな事言えないだろう。がんばれば出来るなんて事、ないのだ。 「中学の時から一緒だからさ、よく先生とか、同級生には『学年一位のヒル魔と二位のでは全然違う』とか言われてたりしたんだ」 「……ヒル魔君、中学の時も一位だったんだ……」 「アイツ、頭いいし、な。先生からしたら俺は扱いやすい優等生、ヒル魔は問題児。これって大きな差だよな」 ヒル魔はズルして一位になっている訳じゃない。そんなの知っている。分かっているつもりだった。だけど俺はどうしても劣等感を感じていた。『なんで俺じゃなくてヒル魔なんだ?』っていう滑稽でバカみたいな劣等感。 アイツは最初、神龍寺高校に入るっていうから、俺も進学先をそこにした。その後、どういう経路で泥門高校受験になったかは知らないけど、ヒル魔がそっち行くというから、俺もギリギリだったけれどそっちに願書を出した。 高校になれば、他の高校ならばきっと難なく(と言うとアレだけど)一位が取れるだろう。だけど、俺はそれでは嫌だった。ヒル魔より上に行きたかった。全国模試で一位を取ったからって上にいった訳にはならない。アイツが受けるとは限らない。同じ学校で、同じ土俵で勝ちたかった。 負けたくないから、アイツには。マケタクナイ。 「姉崎さんは、まだ俺とヒル魔が似てるって思う?」 「……ううん、さっきも言ったとおり、『君は君』に落ち着いたかな?」 「そ、っか」 似てると言われて喜んでいる自分と苛立っている自分がいた。俺ってば、やっぱ自己中心的。折角似てるって言われたのに。 結局の所、俺が蛭魔妖一と同じ訳なかったと言う事。それは中学時代の俺だって否定していたじゃないか。ただ同じ中学校で、同じ高校だっただけ。それだけの接点。だけど、越せないならば、同じになりたかった。負け犬みたいな考えだ。 「君?」 姉崎が俺の顔を覗き込もうとした瞬間、ガラリと大きな音を立てて教室のドアは開く。そこにいたのは金髪の悪魔。 「おい、糞マネ!乳繰り合ってんじゃなくてマネージャーならマネージャーらしく部活しろ!今何時だと思ってるんだ!」 「なっ……!そ、そんな事してませんっ!!」 悪魔にも負けない大声で姉崎は返すと、腕時計を見てようやく今何時かを知る。「ってもうこんな時間…!ご、ごめんね君っ!それじゃあまた明日!」と、ワタワタ慌てながら俺に手を振り廊下を走る。 残されたのは俺と、俺が世界で一番嫌いな男。蛭魔妖一はいつも通り背中に銃器を携え、そして油断ならない目つきで俺を見る。 「久しぶりじゃねーか」 「……ヒル魔が俺の事覚えてると思ってなかった」 「俺の記憶力なめんじゃねーよ、万年二位野郎」 「俺はお前みたいにコネがある訳じゃなくてね」と、まるで揺さぶりをかけるように言ってみるけれど、こいつの学力はこいつの努力でついた事ぐらい知っていた。 「おいそんな口俺に聞いていいのか?中学から一緒のテメエなら俺の情報網がどんなものか分かってるんだろ?」 ヒル魔はケラケラと愉快そうに笑いながら、お得意の真っ黒な『脅迫手帳』をポケットから取り出し、長ったらしくてまるで魔女みたいな指を使いわざとらしく大げさに手帳を捲り始める。「泥門高校2年生、お前の好きな奴は―――」 「姉崎まもり。高1の時から、一目ぼれだった」 俺の方が断然早かった。と思った。 「…………」 「俺が言ってびっくりしたか?それとも、まだ知らなかったか?」 「――サア、どっちだろうな」 ヒル魔は何のつもりか、ゆっくりと手帳を戻した。自分からヒル魔に弱みをいう奴なんていないだろう。きっとヒル魔は少なからず、少しでも、ほんの少しだとしても驚いているだろう。蛭魔妖一を中一の頃から知ってる俺なら分かるこの表情の変化。 俺は少しだけ、『勝った』と言う気持ちになった。嬉しさが少しだけ胸に広がった。そして、他は、悲しさ。「似てる」と言われた時の心境と、ちょっとだけ似ていたような気がした。 「面白しれェ」蛭魔は近くにあった机に体重を預ける。「やっぱ、テメエは俺とそっくりだ」 「……本人様にそんな事言われると思ってなかったよ」 「他の能無し共はお前の本性に気付いていなかったみたいだがな」 「本性?そんな風に言われると嫌なんだけど」 「誰よりも負けず嫌いで他人を見下しているような孤高を持する」 「そんな所、一番お前と似てないじゃないか」 俺はため息をつくように息を吐いた。ニテナイ。フと気付けば俺は、俺が一番聞きたくも言いたくなかった言葉を軽々しく吐いていた。こんなにも言葉と言うものは軽々しくて、そしてバカバカしいものだったのだ。そんなバカげたものを俺はずっと聞きたくて、言って欲しくて。まるで小学生の頃にもらったクリスマスプレゼントを気体するかのような心情。バカバカしい。 「ああ、よく知ってるじゃないか。俺の事」 「そりゃあ中学の時から一緒だから」 「そう、その目だ。俺と似ているのはお前のその目。とって食いなんてしねえのに、まるで俺を見てる時だけその目を見せる。他と話している時は人畜無害そうな表情作って、そういう時だけ猛獣みたいな目になる」 「自分で自分の目を猛獣だっつってんの?」 恥ずかしい奴、と俺は呟いた。そう呟いたことで俺は、ずっと歯を食いしばるように声を出していたのを自覚する。 「……ヒル魔、も、俺の事よく知ってるんじゃん」 「そりゃあ中学の時から一緒だから」ヒル魔は俺の言葉を繰り返した。 「カワイイ女の子に知ってもらえるなら歓迎だけど、お前じゃ嫌だな」 「ハッ、糞マネとかか?」 「へえ、ヒル魔でも女子の事かわいいとか思ってるんだ」 「テメエの視点からしたらそうなるだけだ」 蛭魔妖一と一番仲が良い女子(と言うと少し御幣があるとは思うが)は俺の知っている範囲ではきっと、姉崎まもりだろう。とはいえ、だからって二人が結ばれるとは限らない。姉崎まもりだって友人は多いだろうし、男の友人だっているだろう。高校生活で将来の相手が決まってしまうほど、人生と言うのは簡単ではない。 「ああ、そうだな。姉崎はかわいいと思うよ。俺の会ってきた女子の中で、一番」 「……ベタ惚れじゃねーか」ヒル魔はペラペラ喋る俺を怪しむように見る。 「悪いかよ」 「いや別に。いいんじゃねえのか」 ヒル魔は怪しむ顔をやめて、ニィと笑った。 ああ、やっぱり頑張れば出来るなんてうそだ。俺はこいつより上に行くことなんて出来ない。不可能だ。俺はこうしてこいつに笑顔を向けることなんて出来ないだろう。敗者だから。敗者は歯を食いしばって睨み付ける事しか出来ない。 だけど考えてみれば、がんばればできると嘯くのは通信教育だとか、スポ根漫画とか、ドラマとか、そういう綺麗事の世界だけだ。 なんだ、皆分かってるんじゃないか。がんばればできるがウソだって事。 「ヒル魔」 「あ?」 「俺とお前は、全ッ然ニテナイからな」 「ああ、俺もそう思うぜ」 俺は万年二位の。きっと、絶対に無理だって今日ようやく分かった。ただ一度でも、彼女の碧眼に見てもらえればそれでいいんだ。それしかくらいしか俺には、役は回ってこないのだからか。悲しいほど身の程をしった高校二年生の秋の空は、俺が思っていた以上に優しく俺を受け止めてくれた。 |
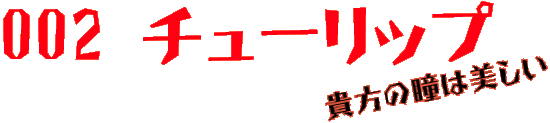
(ほら、だったら頑張れば好きになってもらえるの?)