モルジアナという少女は俺が生まれてから今までで、見たことないくらい凛とした娘だった。 そういう風に説明してしまうと、なんだか彼女が毎度毎度頭を下げなきゃいけないほどのお偉いご身分で俺なんかが目にしては行けない様に思えるが、そうじゃない。彼女は奴隷だ。富裕層様のペットなのだから、そういった意味では触れてはいけないのだろう。まあ、そんな俺はスラムの人間だ。その日暮らしでなんとか生活を賄い、たまに行けそうと感じたのなら盗みだってする。 この世界ではいかんせん、盗られる方が悪いんだ。俺だって俺のモノが盗まれたら怒るけど、不注意だった自分のせいと納得させている。奴隷とスラムではもちろん身分の差は歴然だろうが、それでも低身分同士のどんぐりの背比べだ。使える人がいないクズよりはマシ、と考えているのがバレたら俺は仲間に刺される気がする。 もちろん仲間にだってここまで堕ちたのに大小なりとも理由はある。生まれてこの方ずっとだとか、逃げてきただとだか。つっても、そんな過去設定等、初対面の人間が分かるはずもなく、俺達は『街角のゴミ』と、皆仲良くごっそりと同じ枠組みに入れられるのは仕方のないことだ。 さてさて、モルジアナの話に戻るが、彼女は俺のきっと、半分くらいの生涯しか送ってないのだろう。 この前まで見るたびにニョキニョキとたけのこのように身長は伸びていったが、気がつけばそのスピードは緩やかになり、ひそかな収穫の楽しみは減っていった。別に刈ってた訳じゃないけれど。とはいえ、彼女はまだまだ小さい。そのあたりの平均的な身長など俺は知らないが、それでもまだ2軒隣の娘・アムレットの方が大きく見える。実際に並んで見たことはないので、全て憶測だ。 なぜ関わりのない俺がモルジアナという少女を知っているかというと言うのは大した話ではない。ただ見ただけだ。彼女はこの街の領主の奴隷。彼の悪行は良く知れ渡っている。暴虐非道、極悪凶猛そして無法千万――いや、ここでは彼が”法”なのだろうか?――な彼には誰も逆らわないし頭を下げるだけ。恐ろしく人を遣う事に慣れている。ただの暴君ではないのが末恐ろしいのだ。"不慮の事故"とやらで亡くなった先代の領主と取って代わったのはつい何年か前の話だというのに、ここチーシャンは一大迷宮都市と少しは言ってもいいくらいに急成長した。あれで20歳足らずだというのはあまりにも出来過ぎている。 モルジアナはよく街で買い物をする。アバーヤのように長い丈を翻し(きっとなるべく足の鎖を隠すように)彼女は歩く。ただそれを俺は見ただけだ。頭の上に乗せた籠は自身を潰してしまってもおかしくないほどに果物を乗せて、零さないように器用に歩く様子はなかなか珍しい。奴隷が物が運ぶのはよく見るが、あんな重いものをあんな小さな子が運んでいるのが珍しいのだ。それもヨタヨタなどせずに、安定している。正直言うと、俺だってあれを運ぶというのなら気合を入れなきゃいけない程だ。聞いた噂によると、彼女はナントカという狩猟民族なのだという。強い目元がそのナントカの特徴らしい。そりゃ納得、と言いたいが、それでも俺の中の男が「女性に重いものを持たせるなんて!」と囁いていた。こうしてうじうじ心の中で言うだけの俺ということでもうお察しかと思うが、まあ当然一人呟いていただけだった。 そんな俺の話を酔いの勢いで話してみたのだが、皆がみな、酔狂だと笑った。 * 今日も今日とて街を歩く彼女を路地裏で観察していると、不意に肩を叩かれた。 「または夢でも見てるのか」スラム一の盗人、サイードだ。彼の長い黒髪がバッサバサと風に揺れ、それを煩わしいというように腕の縄で乱暴に、それでも器用に結んだ。 「違ェよ。違う。そう、きっと違う」俺はもちろんの事頭は良くない。 「やめとけ。あの子とついでに大男は領主様のお気に入りだ」 「だから」 「ハイハイ分かってる。……が、狙いが大男の方なら俺は友達辞めるからな」 「……だから」 「睨むなよ」とサイードは笑った。「俺だってあの子は良いと思う。ただあと5年、いや3年は欲しい」 3年。3年経ったら彼女はどう変わるだろうか。身長は伸びるのだろうか。顔つきはすっかり大人のそれになるだろうか。俺は少しワクワクしたが、3年経ったらこの街はどうなるのだろうか、と考えた。今より発展するのだろうか?これが限界だろうか?あの領主ならまだいけるだろうか?街が潤えば俺達の生活も潤う。それは物凄くありがたい。幸せだ。俺は。俺達だけは。 3年経ったところで、彼女は奴隷のままなのだ。 今がどのように扱われているのかは分からない。ただたまに顔や手足の生傷から想像するに、生易しいものではないのは当然だ。なんたってあのジャミルだ。領主邸の近くにいれば怒鳴る声だってよく聞こえる。それに生々しい鈍い音だって。 「3年……か、長いな」 「なんだよ。もっとノってこいよ。楽しみだろ、あの子の3年後」 「そりゃあそうだ。お前なんかよりもずっと」胸が苦しくなるようだ。「心配している」 俺のその一言にあのお喋りのサイードも絶句したらしい。口を開けたまま俺の顔をまじまじと見つめるのが30秒、体感時間にして1時間は過ぎた。「お前、おかしい」それはこいつからも、他からも何度も何度も聞いた。が、次の言葉は予想していなかった。 「まるで父親じゃねえか」 「そんな事ねェよ。あの子が迫ってきたら答えられる」 「そういう家族だってあンだろ」 「それは"普通"じゃねえーよ。俺は普通に」 普通に? 彼女を見る目は一体何なのだろうか。性欲と言えば少し違うかもしれないし、そうかもしれない。如何わしい感情だけを抱いている訳ではないが、例えもし、彼女が頷いてくれるのならば俺は男らしく頂くだろう。でも、今現状そうなるとは思えないし、というか、彼女は俺を知らない。だけど、俺は彼女に俺という人間がこの世に生きて、チーシャンで生活しているという事実を知ってほしい訳じゃない。ただ見守りたい。年端もいかない少女のように俺は恋い焦がれいるのだ。 「穴があったら何とやらというやつか」 「下世話にも程があるな。俺はそんなヨコシマじゃねえっつの」 「んじゃあタテシマか」 「……意味分かんねえよ」 「興味ないくせして、結局触れ合ってんだよ」 「ああ、そう」 * 奴隷解放が命じられたのはそれから間もなくだ。とある旅人の坊主がダンジョンを攻略して、その財宝を使ったらしい。何てお人好しだ。意味が分からない。どのくらいの金を要したのか数には疎い俺には分からないが、その金は今までの領主がしてきたような交渉材料になったはずだ。(ちなみにジャミルは親父とお揃いの"不慮の事故"で亡くなったらしく、形式だけの葬儀が行われた)よそから領主を連れてくる手間も必要なく、旅人の坊主が領主となり、この街を牛耳れたはずだというのに、全く金持ちというのはよくわからないものだ。だがしかし、新しい領主のおかげでここスラムにも少しばかりの陽が灯った。将来的にはここも何とかしたいというのが新領主様のお考えのようだが、それはきっと叶わないだろう。ドブネズミは清潔な場所では生きれない。 「奴隷じゃない女なら気軽に声かけられるじゃねーか」 そう言ったのは誰だったか。気がつけばこの一体で俺を知っている人は俺の視線の先までご存知のようで、会う度に誰かしらに言われた。しかしまあ、簡単に言ってくれる。 彼女は凛とした娘だ。ドブネズミは触れない。 * 「…すみません。そこ、通りたいのですが」 どうやら酔っ払って道路の真ん中で寝っ転がっていたらしい。その声に飛び起きるように俺は大慌てで決して綺麗じゃない髪の毛や衣類を払った。はあ、と息を吐いたもののすぐに吸ってまた吐く。ああそうか、息が荒いのか。 「わ、悪い」 「いえ」 やはり彼女だ。モルジアナは小さく俺に礼をするとくるりと翻した。 どうやら台車を通したかったようで、少し遠くからカラカラと、車輪の廻る音が聞こえた。台車が通っている間、俺は壁に貼り付いたまま、身動き一つしなかった。その様子を、台車を引っ張る人、押している人はちらりと一瞥し、前を向いた。知っていたが、わかっていたが、ゴミを見る目だった。そりゃ勿論、昼間からこんなところで転がっているのなんて、空の酒の瓶くらいのゴミだ。 その中でモルジアナはもう一度俺を見、礼をした。彼女の視線は他を見る目と変わりない。こんな俺にも差別しないで、とか、そういうのじゃないのだろう。彼女からしたら、世界はきっと同じに見えている。そんな目だ。絶望はしないけれど、期待はしない方がいい。 「なんだよ、折角話せそうだったのに」気がついたらサイードが近くにいた。 「……どこがだよ」 「まあこれで顔くらい覚えてもらったんじゃないのか」 「最悪だな」 「ひっくり返れば最高だ」 「楽観的だよな、お前は」 久しぶりに見た彼女は服装が変わっていた。前みたいな、布一枚みたいな服ではなかった。そこそこ丈夫な服で、エプロンまでしていた。立場は大きく変わったけれど、モルジアナ自身は変わらなかった。元々奴隷だったせいかの謙遜する癖は治らないようだし、常に仕事を求めているらしい。おせっかいな仲間からの横流しの情報だけど、俺はそんな彼女に安心した。 勿論、歳相応に笑ったり、無邪気に遊んだりして欲しい気持ちだってあるけれど、俺の中のモルジアナ像はそんなんじゃない。きっと俺は知らぬ内に彼女を神格化している。こうじゃなきゃいけない、とか、こうするべきだ、とか。だからこそ彼女に触れられないし近づけられない。そう思った。 このままでいいのだ。 「そういえば、知ってるか。アリババ様の事」 「ありばばさま?新しい領主のことか?」 「お前なあ…。ダンジョン攻略者の坊主だっつの」 「ああ、あの金髪の」 「そう、そいつ」サイードは持っていた酒を煽った。「荷物纏めて、どっかに行っちまったんだと」 軽く言ったようだが、大ニュースだろう。実際、その、"アリババ"という子供はあまり表舞台に上がることはなかったが、彼はこの街にとっては英雄のようなもので、それこそ奴隷達からすれば神様の様な人だ。アリババがいなければこの街は一生暴君の管下だっただろう。俺だって少しくらい感謝はしている。 「あ」 次はなんだ、と顔を上げると、サイードの視線の先には先ほどすれ違ったばかりのモルジアナがいた。その顔は俺の知っている顔なんかじゃなく、そう、歳相応に、苦しんでいるような顔だった。 「……何があったんだろう」 俺は呟く音で言った。何があった。そんな事なんとなく察する事が出来る。モルジアナはあのアリババと共にダンジョンから出てきた一人なのだ。そして彼女は元奴隷で、その足を豪快に動かして走れるのも皆みんな、鎖を解き放ったアリババ様のおかげだ。 彼女は風のように俺たちの前を通り過ぎた。今から走ったって間に合わないだろうに、彼女は街を駆ける。俺はアリババという人間がどんなのか分からない。モルジアナにとってどれ程の人間かも知らない。だけど、彼女は彼の為にここまで走っているのが現実。 「あーあ」サイードは俺の肩に手を置いた。「こんな時は呑むしかない」瓶を持つ右手を上げた。 「……違ェよ。違う。そう、きっと違う」 「何が」 「そうじゃねえんだよ」 きっと恋なんかじゃない。何度も言ったことだ。何度も思ったことだ。びっくりする程今冷静だし、ただ、彼女はもしかしたらここにはもう戻ってこないかと思うと、少し、ほんの少し寂しいなと思うくらい。ほら、それくらいだ。元々ちょっと遠くから見ていたくらいだし、それは3年後だって変わらない。都合の良い夢なんて見てないし、今日だって別に対して喋れなかったけどそれに対して残念だなとも思っていない。俺はこんなもんなんだ。チャンスが降ってこようがそこから静かに手を引く。慎重で入念で用心深くて、ただの臆病者。 これから一生、モルジアナに会えなくても何も変わらない。そうやって過ごしてきた。あの凛とした娘は娘のまま、俺の中で永遠に変わらない。そう思うとどこか安心できた。 俺の神様はまだ、呼吸をしている。 |
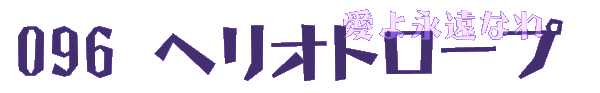
(そうおもうしか、ないのだ)